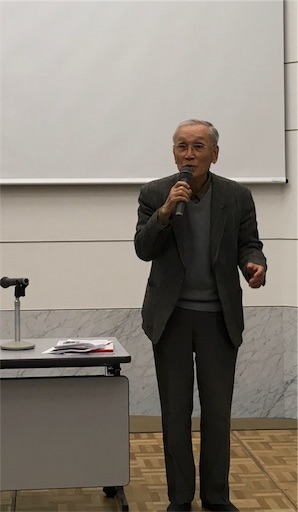明けましておめでとうございます。
昨年も皆さまのご支援・ご厚意により、ささやかではありますが、
会の諸行事を滞りなく終えることができました。
厚く御礼申し上げます。
2020年は被爆75年に当たります。
原民喜によって紡がれた言葉も、益々重みを持つものになってくること
でしょう。
今年も会では様々な企画を予定しております。
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
広島花幻忌の会 事務局長 長津功三良
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
【 冬の関連行事 ごあんない】
新年も色々な行事が行われています。
① 12/1〜1/31 広島市立中央図書館での展示


昨年12月1日より今年1月末まで広島市立中央図書館の2階展示スペースにて、
広島ゆかりの詩人たちの作品や資料などを紹介する展示が行われています。
呉市出身の詩人・黒田三郎 関連資料をメインとしながら、小山内薫、
詩人たちの生涯と作品、広島の近代詩壇の概観を知るには非常に優れた構成
になっています。会期は月末までです。
② 北海道立文学館では民喜資料の展示が始まりました。
(2019年12月20日〜2020年3月22日(日)まで)
昨年末に発見された書簡や遺書などの公開です。
北海道に行かれる便のある方は是非お立ち寄りを。



北海道新聞(2019/11/22)には同館理事長の平原一良さんの解説記事が
掲載されました。

平原さんの解説詳細は、三田文学1月10日号で発表予定です。
発売を楽しみにお待ちください。
http://www.h-bungaku.or.jp/ (開館時間など詳細は北海道立文学館ホームページで。)
③ 広島文学保全の会からのお知らせ
1月1日から12月29日までの会期で、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館にて、
四國五郎さんと弟の直登さんの日記を中心とした展示が始まりました。


館内で上映される映像の音声は、昨年11月に急逝された木内みどりさん
によるものです。
図らずも「遺作」となってしまいましたが、「心のこもった
素晴らしい映像作品になっています」と関係の方々。
木内さん、本当にありがとうございました。
感謝とともに謹んでご冥福をお祈りいたします。

(上の写真は2019年8/15の原爆詩・反戦詩を読む市民朗読会の折のもの。
絵本「おこりじぞう」を掲げる木内さんと、四國五郎さんのご子息・四國光さん)
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
会では原民喜命日(3月13日)にちなみ、今年も3月15日(日)に広島市中央公民館で
花幻忌の集いの開催いたします。

集いには昨年度、原さんや会員のレクチャーを受け、原民喜についての学びを深めた、
平和ガイドグループ Link Hiroshima の方々も参加予定です。
(写真は原民喜について学ぶLink Hiroshimaの皆さん)
詳細は2月の近状通信(会報)やブログでお知らせ致します。
(文学散歩リクエストも沢山の方々から頂いており、
引き続き催行予定です。)
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
皆さまにとって幸多き年でありますように祈念しております。
広島花幻忌の会 事務局電話番号090-9065-5345(長津)
メールアドレス hananomaboroshi@yahoo.co.jp

(写真は昨年12/3 中国新聞に掲載された記事)
#原民喜 #花幻忌 #北海道立文学館 #平和 #被爆75年 #朗読 #被爆75年 #四國五郎 #木内みどり